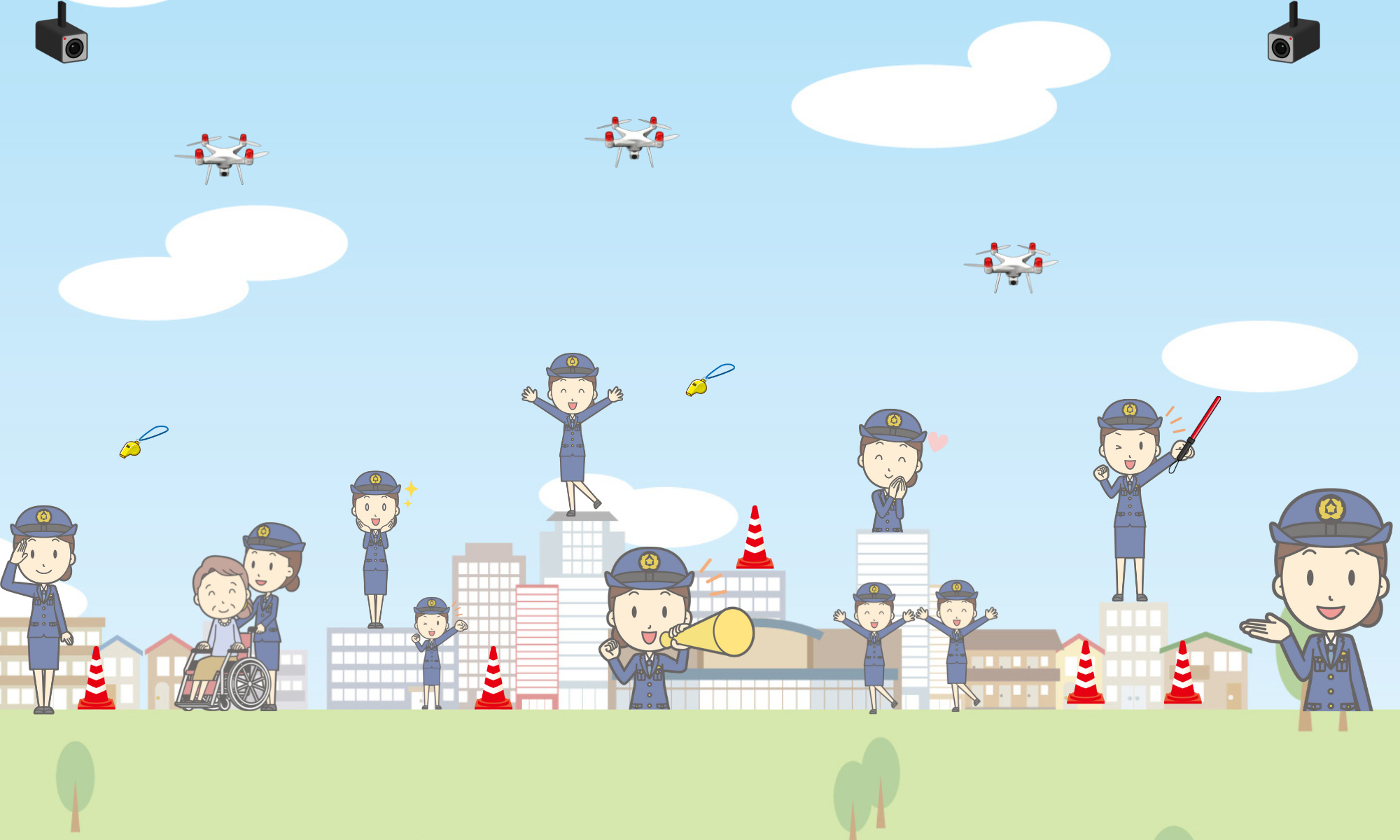施設警備員は現場内での落とし物の対応をする事があります。しかし配属先の現場によっては、落とし物の管理を施設警備員がすることなく、クライアントが管理している所もあります。そうなると現場の経験の仕方によっては、同じ施設警備員とはいえ拾得物の対応のやり方が身に付いていない人も出て来るのです。
施設警備員の拾得物対応
施設警備員は該当施設で勤務する時、拾得物対応をする事があります。
お客様から「落ちてました」と渡され受け取った時、どの様な行動をしたら良いのか、これは配属する現場によってどこまでが施設警備員が管理しているかによって変わってきます。
何も管理する事が無いのであれば、施設の管理者を案内してお客様自身でそこへ持って行ってもらう様お願いしてそこで終了です。
その時に、管理者へ渡す前に報労金を受け取る権利を主張するか確認するよう指示が出ているのであれば、目の前のお客様へ確認をします。
この時の報労金制度は、落とし物の種類によって権利の無いモノもあるので注意が必要です。
こういった知識は、施設警備員として教育を受ける時にある程度は講師の方から指導を受けていると思うので、何となくはお分かりだと思います。
同じ警備員なのに経験に違いが出る
施設警備員とはいえ、現場によっては拾得物の対応をほとんどしない所もあります。
一応、拾得物の対応を警備業者に一部任せている所でも、1日当たりの拾得物が殆ど無いと、警備員としての拾得物の経験値が積めません。
今の現場では、落し物はクライアントか警備員のどちらでも受け取る事が出来るのですが、警備員へ落とし物が届けられる頻度は、半年に1件あるかどうかです。
これは普通の施設警備の現場と比べても、非常に少ないと思います。
以前のヒマな現場でも1か月に数件はありましたし、大型商業施設勤務の当時では、1日で数十件という具合です。
これほど対応件数に差があると、同じ施設警備員といっても拾得物対応の知識と経験にものすごい開きが出来ます。
別々の現場で、それぞれの警備員さんを見てきましたが、明らかに落とし物というものに不慣れな警備員さんは、稀に上がって来る落とし物に対して見ていて不安になるほどです。
確認するべき事、聞くべき事柄が抜けている事が多かったですね。
施設警備の現場に配属する時は、ある程度拾得物の対応が多い所は一度は経験しておいた方が良いと思います。
警備業法としての範囲の知識のみ
新任教育や、現任教育などで遺失物法に関した指導を受けた事はあるかと思います。
しかし、座学で聞かされてもなかなか頭に入る事は無く、やはり現場で実際に経験するのが一番だと思います。
それでも、勤務している現場が「ほとんど落とし物が来ない」様な現場で実践も難しいでしょう。
そうなるとやはり座学でしか学べなくなってしまいますね。
ですが、何も学ばないよりは少しでも頭に入れておく事は無駄ではないので、警備業法として聞いた事がある、位の程度でも良いので身に付けておく事をおススメします。
貴重品などの落とし物があった時の報労金制度や、落とし物を預かっている期間を過ぎると所有権が無くなるのはどのくらいか、など現任教育の時でもお話はあるかと思います。
配属先の現場で殆ど拾得物対応の無い人でも、最低限の事で良いので、遺失物法というものは理解しておいた方が良いですね。