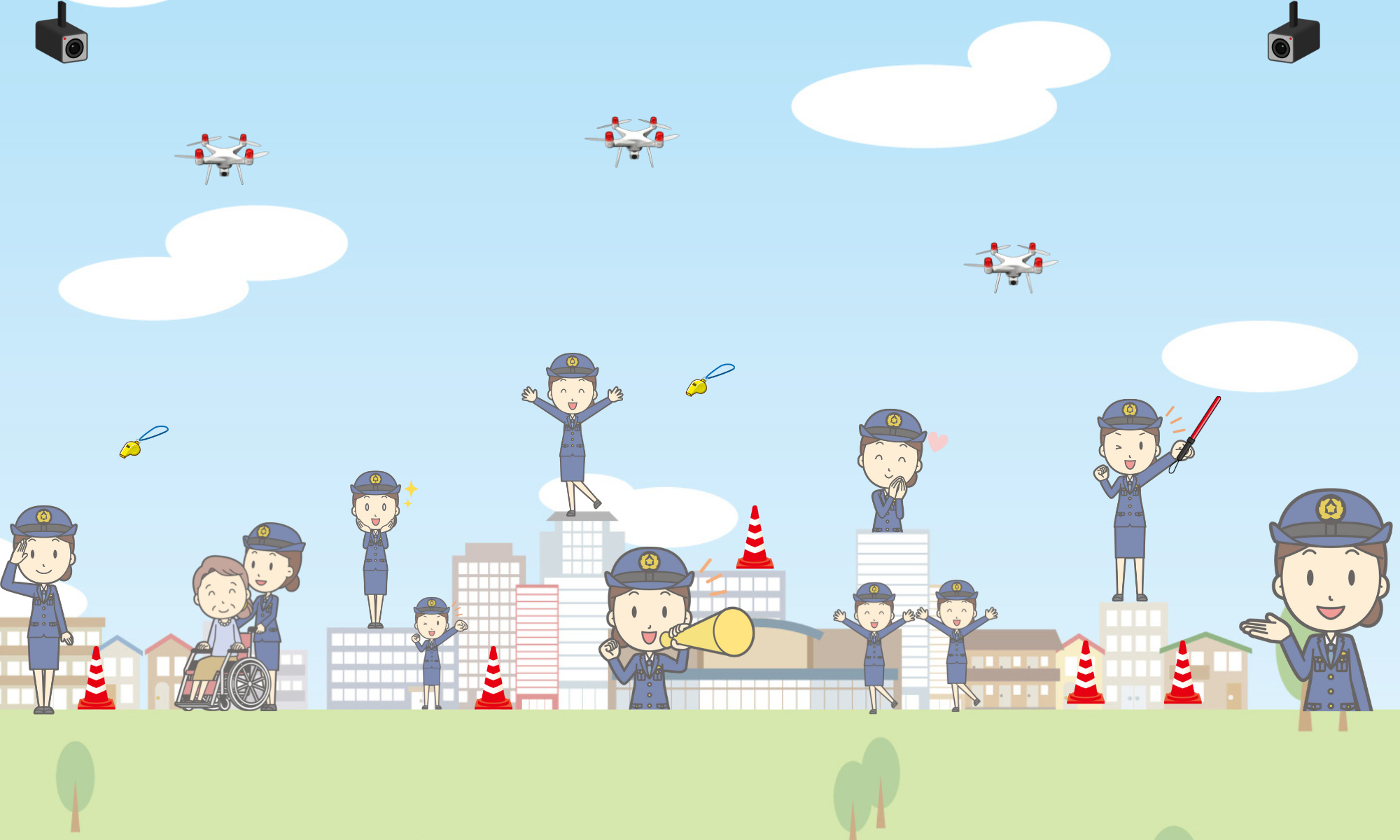施設警備員として商業施設勤務当時、自動ドアの正常作動確認をしていました。それまでは「開いて閉まれば問題ないよね」と単純に思っていましたが、実際先輩警備員から指導を受けた時、これほどまで細かいのかと感心したものです。構造上、内側と外側にセンサーが付いているので、片側だけのセンサーで開いた事を確認するだけではいけないのです。
自動ドアの作動の仕組み
自動ドアは今やどこの建物にも普通にあります。
特に施設警備員は常駐している様な建物となると、大抵自動ドアは備え付けられているのではないでしょうか。
そして自動ドアが設置されている現場では、警備員が起動や停止の業務を任されている場合が多いです。
この自動ドアですが、多くの場合はドアの天井部にセンサーが付いており、人が近づくとそのセンサーが反応してドアが作動します。
更に、作動するドア部分にもセンサーが付いており、人や物がドアのレールの線上にある時、センサーが感知してドアが閉まらない様にもなっています。
これらの仕組みで、人が通る時スムーズに自動ドアが作動する様になっているのです。
施設警備員は巡回時にこの自動ドアが正常に作動しているか確認もしているのです。
警備員の自動ドアの確認方法
施設警備員が巡回時に自動ドアの確認をするとき、利用者が問題なく自動ドアを通る事が出来る様確認しているのです。
まず、自動ドアがどの様な仕組みで作動しているのかという事を理解しておかなければ、正しい確認は出来ないでしょう。
自動ドアは扉の手前と扉の向こう側の天井部にセンサーが付いています。
これはどちら側から人が来ても、センサーが反応してドアが開く様に出来ているからです。
この時、警備員が自動ドアの確認をする時は、まず手前側のセンサーを反応させて扉を開き向こう側へ通り抜けます。
そしてセンサーの反応から外れるほど離れ、ドアが閉まるのを確認するのです。
その後、再度センサー内まで近づき扉を開け元の場所まで通り抜けます。
この時、またセンサーから外れるほど離れてドアが閉まるのを確認するのです。
ようするに
内側のセンサーが反応して開くのと閉まるのを確認後、外側のセンサーで開くのと閉まるのを確認する
この4つのドアの動作を確認するのが自動ドアの正常作動確認だと教わりました。
自動ドアの確認と聞くと単純に、その場に立って開くのを確認するだけ、という警備会社もあるかもしれませんね。
そこまで細かい指導をしているのか
以前の現場では、配属した現場で先輩警備員から研修を受けた時、自動ドアに関する正常作動確認の指導は受けませんでした。
この時、私自身は商業施設での指導経験があったので他の人はどうか別にして、自動ドアの仕組みや確認方法は身に付いていました。
現場のクライアントが自動ドアの管理について警備員に対してそこまで期待していなかったリ、管理を警備員に任せていない場合、警備員は自動ドアの仕組みを学ぶ事はありません。
これだけで、仕組みを学んだ警備員とそうで無い警備員で差が生まれる事になります。
こういった経験の差が、意外な所で発揮される事もあり、身に付いている警備員さんは何かの切っ掛けでクライアントに良い印象を与える事もあるのです。
学ぶ機会が無ければずっとそのままである、という事も過去の現場でいくつか見てきました。
何も知らない警備員さん本人が悪いわけではありませんが、学ぶ機会が与えられないというのは、配属された現場で自然と差が出来てしまうのだという事を理解しておく必要があります。
もし現場配属の選択の機会が与えられる事があるのなら、どんな現場の配属を希望しますか?